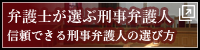麻薬特例法がもたらす薬物捜査の「闇」①
2025年7月
弁護士 金 子 達 也
1 麻薬特例法は、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」といいます。
その名の通り、薬物犯罪を助長する行為等を防止するため、薬物犯罪の収益を剥奪する規定を設けたり、薬物犯罪に関する刑罰の特例を定めたりする法律です。
この法律は、刑事弁護人の目線で見ると、捜査機関に濫用的・脱法的に利用されている側面も否定できない「やっかいな法律」とも言えますので、これから2回にわけて、その一例を紹介し ます。
2 麻薬特例法8条1項は「薬物犯罪を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け,又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する」と規定しています(規制薬物「として」所持等罪)。
また、麻薬特例法9条は「薬物犯罪(中略)を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は,3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています(薬物犯罪の「あおり」又は「唆し」罪)。
これらの規定に共通しているのは、行為者が規制薬物を実際に所持したりしていないのに、そのような意思を持って行動したり、行動を唆したりするだけで、処罰されてしまうものであるということです。
3 しかも実務上、これらの規定そのもので処罰されるケースは希です。
むしろ、これらの規定は、規制薬物が「あるかもしれない」との見込みだけで、捜査機関が捜索等を行うための「ネタ」として濫用されていることの方が、多いとさえ言えます。
このことについては、筆者が以前、当事務所ホームページに掲載したブログ「冗談のつもりだったのですが,インターネットで氷砂糖を「覚醒剤」だと嘘を言って売ったことが警察にばれてしまいました。私は何か罪に問われますか?」でも詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
4 更に言うと、10年くらい前までは、税関検査で旅行者の所持品から規制薬物が発見されて捜査が開始された麻薬(覚醒剤)密輸事案(携行型の密輸事案)の捜査において、最初は麻薬特例法8条1項の規制薬物「として」所持罪で逮捕勾留し、その後に麻薬(覚醒剤)取締法、関税法違反(麻薬等密輸罪)で逮捕勾留するという捜査手法が良く使われていました。
つまり、当時の捜査機関は、税関検査で規制薬物が発見された以上は麻薬(覚醒剤)密輸罪の嫌疑が濃厚であるはずなのに、敢えて本丸である覚醒剤取締法、関税法違反(覚醒剤密輸罪)ですぐに逮捕勾留することを避け、最初は比較的微罪である麻薬特例法8条1項の規制薬物「として」所持罪で逮捕勾留し、引き続き本丸の麻薬(覚醒剤)密輸剤で逮捕勾留することにより、根っこは同じ規制薬物の密輸という犯罪行為について、2度の逮捕勾留を重ねて時間稼ぎをする「荒技」をやってのけていたのです。
もっとも、携行型の密輸事案にあっては、このような手法を最近では見かけなくなりましたので、もしかしたら捜査機関もこれが「脱法的」であると気付いたのかも知れません。
ただ、コントロールドデリバリー捜査が行われたような場面では、今でも、このような手法が使われているので、次回は、このことについて解説します。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★