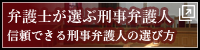脱税行為が刑事事件として処罰されるのはどのような場合でしょうか
弁護士 金子達也
1 令和7年6月に国税庁が公表した「令和6年度 査察の概要」をもとに、脱税行為が刑事事件として処罰されるのはどのような場合なのかを見てみましょう。
2 査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的とするものといわれています。
この査察制度を担うのは、国税査察官(国税庁に所属して脱税調査やその告発を行う専門職)です。国税査察官は、悪質な脱税行為を行う納税者に対し、裁判所の許可を得て強制調査(捜索・押収)を行うことができる強い権限が与えられています。
国税査察官は、査察調査の結果、調査対象者には刑事処罰をもって望むことが相当と判断した場合は、検察官に対し、対象者の刑事処罰を求める告発(ここでは「刑事告発」といいます。)を行います。
この刑事告発を受けて、検察官は、当該事案を脱税事件として捜査・起訴するのです。
3 冒頭で紹介した資料によると、令和6年度に国税査察官が検察庁に告発した件数は98件で、脱税総額(告発分)は82億円でした。1件あたりの脱税額は8400万円、告発率(査察調査を行ったものの中で告発に至った案件の割合)は65.3%でした。
また、この資料によると、令和6年度中に一審判決が出た99件の全てに有罪判決が言い渡され、そのうち13名に実刑判決が言い渡されました。実刑判決を受けたもののうち、査察事件単独で最も重いものは懲役2年6月でした。
4 この資料では、令和6年度においては、査察制度の目的に鑑み、特に、消費税事案、無申告事案、国際事案などの、社会的波及効果が高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組んでいるところであるが、特に消費税に対する国民の関心が高いことを踏まえ、消費税事案について積極的に取り組み、令和6年度には29件の消費税法違反の事案を告発したと報告されています。
実際、上記3の実刑判決を受けた13名のうち、消費税法違反を含むものが7人であったとも報告されています。
5 かの有名なアル・カポネも脱税が摘発されて刑務所に服役した時期がありました。
査察調査を受ければ、追徴課税や重加算税などの制裁的課税を受け、脱税までして温存したはずのお金以上の大金を失うばかりか、刑事告発されて刑務所にも服役させられるリスクをはらんでいるのです。
6 他方で、査察調査が入った場合の告発率が65.3%であったということは、裏を返せば、万が一、査察調査を受けた場合であっても、そのうち約35%の事案は告発までには至らずに済むということになります。
筆者は、かつて大分地検三席検事の立場で、国税査察官のカウンターパートとして、脱税事件の捜査・公判を指揮担当していた時期がありました。
そのときの縁が続き、弁護士となった今でも、国税査察官OBで今は税理士として活躍している盟友と協同して、積極的に脱税事件の弁護に取り組んでいます。
その場合、常に約35%の可能性(告発されない可能性)を追求することにしています。
つまり、査察事件の実情を踏まえて想定される「告発基準」を念頭に置き、まずは、簿外経費主張などの積極的な防御活動を展開し、認定され得る脱税額をできるだけ圧縮するための努力を重ねて、刑事告発の回避を目指して動いているのです。
もし、査察調査を受けた、あるいは受けるおそれがあると感じたときは、お気軽に御相談ください。
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★