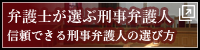麻薬特例法がもたらす薬物捜査の「闇」②
弁護士 金 子 達 也
1 麻薬特例法3条、4条では、日本に輸入されようとする貨物に隠匿された規制薬物を取り除き、又は取り除かないで当該貨物を流通させて監視する措置(コントロールド・デリバリー)を執るための上陸及び税関手続の特例措置を定めています。
法律の条文自体が長大でわかりにくいのですが、簡潔に言うと、これらの規定は、規制薬物密輸事案の捜査のために必要がある場合には、警察等の捜査機関が、入国審査官に要請して(本来なら上陸許可できない)捜査対象者を日本に上陸させることができたり(3条)、税関長に要請して(本来なら輸入許可できない)捜査対象貨物を日本に輸入させることができる(4条)とされているのです。
そして、この特例により、捜査機関は、当該捜査対象者や捜査対象貨物を監視下に置きつつ日本国内で行動させ(泳がせ)、密輸組織の指示者や拠点を突き止めて一斉検挙につなげるコントロールド・デリバリー捜査を行うことが可能になったわけです。
2 なお、この捜査を行う場合には「薬物を取り除き」又は「取り除かないで」当該貨物の流通を監視することになりますが、前者を「クリーン・コントロールド・デリバリー」といい、後者を「ライブ・コントロールド・デリバリー」と言います。
両者の使い分けですが、一般には、監視対象者が逃走等して結果的に規制薬物が日本国内に拡散されてしまう危険を防止するため、可能な限り「クリーン」で行うことが原則のようです。
一方、複雑に梱包等されており薬物を取り除くことが不可能とみられたり、そのための作業時間をかけると犯罪組織に気付かれる危険があるような場合には、「ライブ」で行う場合もあるようです。
3 残念なことに、コントロールド・デリバリー捜査が行われた場合は、今でも、まず対象者を麻薬特例法8条で逮捕勾留し、それにより対象者を相当期間身柄拘束をした後に、改めて麻薬(覚醒剤)取締法・関税法違反(覚醒剤等密輸剤)で逮捕勾留するという、同じ根っこの犯罪に2度の逮捕勾留を重ねる脱法的手法が使われています。
実際、筆者が最近国選弁護を担当した同種案件でもこの手法が用いられました。
残念ながら、裁判所も、規制薬物捜査の必要性を優先させて、問題あるこの手法を黙認しています。
刑事弁護人にとっては、裁判所の理解が得られないため、この大きな「闇」の世界が改善できず、忸怩たる思いでいるところです。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★