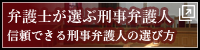仮想身分捜査
弁護士 虫本良和
2025年(令和7年)6月、警視庁が、いわゆる「仮想身分捜査」を全国で初めて実施し、特殊詐欺事件の容疑者を検挙したとの発表を行いました。
この「仮想身分捜査」については、同年1月23日に、警察庁刑事局長名義で発せられた「仮装身分捜査実施要領の制定について(通達)」(警察庁丙刑企発第1号)で定められた「仮想身分捜査実施要領」において、ガイドラインが示されています。
このガイドラインによれば、「仮想身分捜査」の定義は、「捜査員が犯罪の実行者の募集に応じて犯人に接触するに際し、当該捜査員のものとは異なる顔貌、氏名、住所等が表示された文書等(以下「仮装身分表示文書等」という。)を提示して行う捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。)をいう。」とされています。
また、仮想身分捜査は「インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとする」として、対象とする犯罪類型を限定し、かつ、「対象犯罪の捜査のため必要であって、他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること。」とされています。
このガイドラインに従った仮装身分捜査を用いる捜査手法として、特殊詐欺グループが「闇バイト」などと呼ばれる犯罪行為の募集を行っていることが発覚した際に、捜査員が当該募集に応じるふりをして犯行グループに接触して検挙することを目指す、いわゆる「雇われたふり作戦」を行う際に、「偽造」した運転免許証や学生証等を示すといったケースが想定されているようであり、今回発表されたケースもそのような事案でした。
このような捜査手法に一定の合理性や有用性が認められることは否定できませんが、今後同様の捜査が全国で実施されるということになるのであれば、上記のガイドラインで示された「対象犯罪の捜査のため必要であって、他の方法では犯人を検挙し、犯行を抑止することが困難と認められる場合に、相当と認められる限度において実施すること」という実施条件が適切に遵守されているかをチェックし続ける必要があります。
この点、いわゆる「おとり捜査」の適法性に関する判断が示された最決平成16年7月12日(刑集58巻5号333頁)は、「少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される」と判示しています。言い換えれば、元から犯罪を行う意思を有する者に「機会を提供する」に過ぎない場合には任意捜査として許容され得るけれども、捜査機関が、相手の犯罪行為を行う意思を助長するような場合は、任意の捜査として許される限度を超えているという判断を示したものとされています。
新たに導入された仮想身分捜査についても、この最高裁の判断を念頭におきながら、不適法な運用がなされないか注視していく必要があります。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★